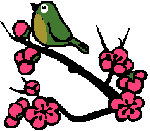|
|
■【今日の写真】 早春の京都 詩仙堂
史跡「詩仙堂 丈山寺」 石川丈山は、隷書、漢詩の大家であり、わが国における煎茶(文人茶)の開祖と言われている。
丈山は、家康に仕え武勲をたてただけでなく、平素から読書に親しみとくに詩を好みました。(詩仙堂ウェブサイトより)
私が撮影した詩仙堂の写真 http://www.glomaconj.com/butsuzou/meisho/kyoto/kyoto_shisendou.htm
|
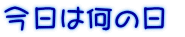 3月11日 3月11日 |
■ 東日本大震災
2011(平成23)年3月11日午後2時46分、三陸沖でM9.0の巨大地震(東日本大震災)
マグニチュード9.0の地震とは・・・・・ どなたも驚かれたと思います。津波被害の甚大さも、原発の恐ろしさも見せつけられました。被害に遭われた方には、心よりお悔やみ申し上げます。
私どもでは、大過はありませんでしたが、ちょうどAdobe Acrobatで作業をしていて、大きく揺れたときに何か起こったのか、Adobe Acrobatのシステムがおかしくなってしまいました。その時に立ち上がっていた複数のファイルが壊れてしまいました。幸い、バックアップで難を逃れることはできました。
海外出張中の息子の部屋の書棚から中身がほとんど飛び出し、小型テレビが落下、息子が戻るまで整理ができませんでした。地震対策が不十分だった結果です。
家宝と言うほどではないのですが、伊万里焼の花瓶がわれてしまいました。また、スエーデンの友人からいただいたガラス細工も無残な姿になってしまいました。
公共交通機関が動かなくて、帰宅困難の問題がクローズアップされましたね。
被災された方々には、改めてお見舞い申し上げます。
|
■ パンダ発見の日
1869年、中国・四川省の民家で、伝道師として日本にやってきた、フランス人神父アルマン・ダヴィドが、白と黒の奇妙な熊の毛皮を見せられました。
ダヴィドはパンダ (panda) のレプリカ標本をパリの自然歴史博物館に送り、これが契機となり、広くパンダの存在が世界で知られるようになりました。
パンダといいますと、ダヴィッドが見つけた白と黒の動物を連想すると思います。
「熊猫」という漢字が当てられますが、その名の通り、「ネコ目(食肉目)熊科」に属するパンダで、正式には「ジャイアントパンダ」ということはよく知られています。
実は、パンダと呼ばれる動物は、これ以外に「レッサーパンダ(レッサーパンダ科)」がいることをご存知の方は多いですね。
食肉目に属していますが、ご存知の通り、竹を主食としています。草食適応を果たしたといわれます。
ちなみに、上野動物園のパンダは、年間1億円で、中国からレンタルしているそうですね。
|
|
■ その他
|
|
【経営コンサルタントの独り言】
■ 宝永大地震は関東から九州まで
江戸中期、約300年前の宝永4年(1707年)に宝永大地震が発生しました。
東日本大震災までは、日本史上最大の地震といわれていました。
M8.7の津波は関東から九州まで及び、太平洋側はもちろん、瀬戸内海沿岸まで大きな被害が出ました。
また、大地震の49日後には富士山が噴火。江戸まで火山灰が降り積もりました。
江戸時代は、それまで土地をどんどん増やし、収穫を得る成長社会でしたが、それが転換され、品種改良や新しい肥料の開発で、限られた土地から多くの収穫を得るようになりました。
日本は、いろいろな自然災害を経験してきています。
しかし、災害にも負けず、復興を果たしてきています。
一方で、その陰でいまだに苦しんでいる方も多数いらっしゃいます。
宝永大地震では瀬戸内海まで津波に襲われたと言われていますので、もし東南海地震などが発生したら、現代の日本の被害は宝永大地震のそれとは比較にならない大きさではないでしょうか。
参考資料: J−NET21
|
| ↑ Page Top |
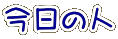 |
|
■ 武田勝頼没
たけだ かつより
天文15年(1546年)−天正10年3月11日(1582年4月3日)
戦国時代から安土桃山時代にかけての甲斐国(現山梨県)の戦国大名で、甲斐武田家第20代当主、通称は四郎です。
信玄の正妻の子ではないために、性差の子供のように信玄の「信」の字を与えられず、後継者ともみなされていませんでした。当初は、高遠諏訪氏を継ぐことになり、諏訪四郎勝頼と呼ばれました。また、信濃国伊那谷の高遠城主であったことから、伊奈四郎勝頼ともいいます。
武田信玄といえば、戦国武将を代表する一人ですが、信玄死後を引き継いだ武田勝頼の評判はあまり芳しいものではありません。
しかし、戦国時代に詳しい歴史家の多くは、巷の評判ほど、無能ではなかったといわれています。
信玄の死後、18城を勝ち取るなどして、初めは勝頼を軽視していた武田軍団二十四将も、次第に勝頼を理解するようになり、結束してゆきました。あの織田信長に「勝頼、侮るべからず」と言わせるほどでした。
信玄が死の床で、勝頼に「信長・家康と闘うようなことが起こったら、自領に引き込んで闘え」と遺言したそうです。ところが、18城を勝ち取るなど、成功体験からの驕りでしょうか、設楽が原の戦いでは敵地に赴いて、信長・家康と闘うことになりました。
信長の「三段撃ち」で有名な設楽が原は平地での合戦です。(歴史研究者の中には、三段撃ちは、実際にはなかったといわれています。)
武田軍は、山地での戦いを強みにしていました。あまり、経験の多くない平地での戦い、銃対騎馬軍団という、新旧の戦法の差などもあり、勝頼は、武田武将の大半を失う惨敗に終わりました。これが、武田一族の滅亡に繋がるといわれています。
勝頼の敗北、武田氏の滅亡は、騎馬軍団と勇猛な武将による成功体験に固執しすぎて、新しい時代の幕開けを読み切れなかったところにあるように、素人考えを持っています。
■ 上杉 鷹山 海外でも知られる日本を代表する名君
うえすぎ ようざん 上杉 治憲(うえすぎ はるのり)
寛延4年7月20日(1751年9月9日)− 文政5年3月11日(1822年4月2日)
江戸時代中期の大名で、出羽国(山形県)米沢藩9代藩主でした。上杉謙信という名門の家柄でしたが、領地返上寸前の財政難に陥っていました。その米沢藩再生のきっかけを作り、江戸時代屈指の名君として知られています。諱は初め勝興、後に治憲となりますが、藩主隠居後の号である鷹山の方が著名です。
宝暦13年(1763年)より尾張国出身の折衷学者細井平洲を学問の師と仰ぎました。
10代将軍徳川家治より「治憲」の名を賜り、明和4年(1767年)に家督を継ぎました。
家督を継いだとき、上杉家は、18世紀中頃には借財が20万両(現代の通貨に換算して約150億から200億円)に累積していました。
初代藩主景勝は、越後で120万石時代に従えていた家臣団6千人をそのまま、石高が15万石で召しかかえました。このため他藩とは比較にならないほど人口に占める家臣の割合が高かったことから、人件費だけでも藩財政に深刻な負担を与えていたのでした。
加えて農村の疲弊や、宝暦3年の寛永寺普請による出費、宝暦5年(1755年)の洪水による被害が藩財政を直撃したのです。
名家の誇りを重んずるゆえ、豪奢な生活を改められなかった前藩主・重定は、藩領を返上して領民救済は公儀に委ねようと本気で考えたほどであったと伝えられています。
藩主に就任した鷹山(治憲)は、民政家で産業に明るい竹俣当綱や財政に明るい莅戸善政を重用しました。当然のことながら、先代任命の家老らと厳しく対立することになりました。
江戸での仕切料(生活費)を8分の1に減額、奥女中を50人から9人に減らすなどの倹約を行ったりしました。
天明の大飢饉では、東北地方を中心に餓死者が多発しましたが、鷹山(治憲)は、非常食の普及や藩士・農民へ倹約の奨励などの対策に努めました。自らも粗衣粗食でした。
曾祖父による学問所を藩校・興譲館として、細井平洲・神保綱忠によって再興させ、藩士・農民など身分を問わず学問を学ばせました。
日本を代表する君主であるだけではなく、ジョン・F・ケネディ大統領の尊敬をうるほど、海外でもその名君ぶりは知られています。
【カシャリ! ひとり旅】 上杉神社
http://www.glomaconj.com/butsuzou/meisho/yamagata/yamagata-yonezawa/yamagata-yonezawa12.htm
|
【 注 】
「今日は何の日」「今日の人」は、Wikipedia、富山いづみ氏のサイト、他を参照し、独自に記載したものです。従いまして、当サイト及びブログ等々に関しては、無断複製転載及び模倣を固くお断り申し上げます。 |
| ↑ Page Top |
昨日   明日 明日 |
| |
| ↑ Page Top |