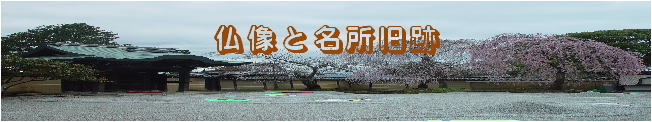 |
|||||||||||||||||||||
| HOME 仏教 仏像 名所旧跡 スナップ グロマコン 経営コンサルタント | |||||||||||||||||||||
私が訪れた名所旧跡です。 ケイタイやスマホのカメラで撮影したものもありますので画質があまりよくありません。 私の限られた感性での写真ですので、たいした作品でもありません。 自分自身の作品を、自分のために整理したものです。 |
|||||||||||||||||||||
| 奈良県 奈良公園 興福寺 | |||||||||||||||||||||
| 公式サイトへのリンク | |||||||||||||||||||||
興福寺(こうふくじ)は、奈良県奈良市登大路町(のぼりおおじちょう)にある、南都六宗の一つである、法相宗の大本山寺院です。南都七大寺の一つに数えられる、奈良を代表する寺院で、世界遺産の一つです。 その前身は、飛鳥の「厩坂寺(うまやさかでら)」であり、さらにさかのぼりますと天智朝の山背国「山階寺」が起源となります。 山階寺は、天智8年(669)に、藤原鎌足が重い病気を患った際に、夫人である鏡女王が夫の回復を祈願して、釈迦三尊、四天王などの諸仏を安置するために造営したものと伝えられています。この名称は、今日でも興福寺の別称として使われています。 壬申の乱(672)ののち、飛鳥に都が戻った際に、山階寺も移建され、その地名を取って厩坂寺とされました。さらに、平城遷都の際、和銅3年(710)藤原不比等の計画によって移されるとともに、「興福寺」と名付けられたのです。 天皇や皇后、また藤原氏の人々の手によって次々に堂塔が建てられ整備が進められ、奈良時代には四大寺、平安時代には七大寺の一つに数えられるまでになりました。 |
|||||||||||||||||||||
所在地 奈良県奈良市登大路町48番地 山号 無し 宗派 法相宗 寺格 大本山 本尊 釈迦如来 創建年 天智天皇8年(669年) 開基 藤原不比等 札所等 西国三十三所第9番(南円堂) 南都七大寺第2番 西国薬師 四十九霊場第4番(東金堂) 神仏霊場巡拝の道 第16番 大和北部八十八ヶ所霊場 第62番(菩提院) 文化財 五重塔、木造弥勒仏坐像、乾漆八部衆像ほか(以上国宝)、南円堂、木造薬王菩薩、薬上菩薩立像ほか(以上重要文化財) アクセス 近鉄奈良駅 東改札より徒歩 JR奈良駅 奈良交通市内循環系統に乗り5分県庁前下車 |
|||||||||||||||||||||
| ↑ Page Top | |||||||||||||||||||||
| 興福寺 中金堂 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ↑ Page Top | |||||||||||||||||||||
| 興福寺 諸堂宇 | |||||||||||||||||||||
| ↑ Page Top | |||||||||||||||||||||
| 東大寺を知る |
|||||||||||||||||||||
| ↑ Page Top | |||||||||||||||||||||
| Copyright© N. Imai All rights reserved | |||||||||||||||||||||